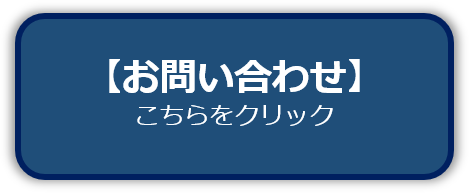「クロスボーダー収納代行」への規制とは(1)
【中央省庁の元法制度担当の弁護士による解説コーナー ~資金決済法編~】
[キーワード:資金決済法、為替取引、収納代行、クロスボーダー収納代行]
令和7年(2025年)6月に「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同法により資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)が改正されました。
主な改正内容としては、次の点があります。本稿では、①の「クロスボーダー収納代行への規制導入」について説明させていただきます。なお、本稿は、シリーズ連載になりますので、続編があります。
① クロスボーダー収納代行への規制導入
➁ 資金移動業者の破綻時における利用者資金の返還方法の多様化(履行保証人債務引受契約・履行保証人保証契約・履行保証金弁済信託契約)
③ 電子決済手段(ステーブルコイン)・暗号資産サービス仲介業の新設
④ その他(暗号資産交換業者への当局による国内保有命令の導入、特定信託受益権の裏付け資産に係る国債運用の容認)
クロスボーダー収納代行とは「収納代行」の一種となりますが、まずは、この「収納代行」について、これまで主にどういう議論があったのかをご紹介します。
なお、「収納代行」という用語は、法律用語ではありませんが、金銭債権を有する債権者から委託又は債権譲渡を受けて債務者から資金を収受し、当該資金を直接輸送することなく債権者に移転させる行為が、典型的なものと考えられているようです。(※)
(1)資金決済法制定時(平成22年/2010年)
平成22年(2010年)に資金決済法が制定されましたが、この資金決済法によって、それまで銀行等の預金取扱金融機関のみが行えた為替取引を、同法による資金移動業者の登録を受けた者も行えるようになりました。これは、当時は大きな法改正だったのですが、「為替取引」に似たようなものとして、当時から「収納代行サービス」、「代金引換サービス」、「回収代行サービス」等が注目されていました。当時の具体的な意図は必ずしも明らかではありませんが、資金決済法を制定するに際して、これらの収納代行サービス等についても、資金決済法の規制対象にすべきではないかという議論がなされていました。
その際の議論の経過は、以下の報告書や議事録等を確認できますが、この報告書を見ると、「為替取引として規制すべき」という意見と、「規制の必要がない」という意見が対立していることが分かります。
平成21年1月14日付け「資金決済に関する制度整備について ―イノベーションの促進と利用者保護―」(金融審議会金融分科会第二部会)
そこで、このときには「性急に制度整備を図ることなく、将来の課題とすることが適当と考えられる。」として、一度、議論を棚上げしているようです。もっとも、その部分のただし書で、「制度整備を行わないことは、利用者保護が十分であることを意味するものではなく、収納代行サービス等が銀行法に抵触する疑義がないことを意味するものでもないと考えられる。」との記載もありますので、将来の制度化の余地を残していたのだろうと思われます。
今回の記事はここまでです。次回は、令和2年(2019年)の割り勘アプリへの規制導入時の際の議論を紹介させていただきます。
※ 2019年12月20日付け「金融審議会 決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ 報告」P16 脚注13
記事作成・監修:弁護士 境 孝也
(なお、本記事は、執筆者が過去に所属・関与し、又は現在所属・関与する組織・機関の見解を記載するものではなく、執筆者の個人的な見解を記載するものです。)
【関連情報】
クロスボーダー収納代行にご関心のある方は、以下のセミナー情報もご確認ください。
金融財務研究会主催
「収納代行ビジネスに関する最新情報と今後の事業継続のポイント 〜クロスボーダー収納代行への規制概要と今後の見通しの解説〜」
(2025年9月16日 (火) 13:30〜15:30、講師 さかい総合法律事務所代表弁護士 境 孝也)https://sakailaw.jp/article/20250724/01/
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k252585
収納代行に関するご相談は、専門知識豊富な弁護士が在籍する弊所まで、お問い合わせください。